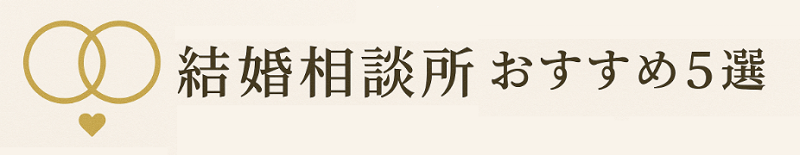結婚相談所は真剣な出会いをサポートしてくれる存在ですが、中には入会を強く勧めてくるケースもあります。
資料請求や無料カウンセリングをきっかけに、何度も電話やメールが届き、対応に困る方も少なくありません。ここでは、しつこい勧誘をスムーズかつ角が立たないように断る方法をまとめます。
目次
あいまいな返事を避ける
結婚相談所からの勧誘を断る際、つい角を立てないように言葉を選びすぎてしまう人は少なくありません。
しかし、あいまいな表現は逆に「まだ可能性がある」と受け取られ、営業の連絡が長引く原因になります。
しつこい勧誘を防ぐには、最初の段階で明確な意思表示をすることが何より重要です。
なぜあいまいな返事は避けるべきか
営業担当は、はっきり断られない限り「見込み客」として連絡を継続します。
次のような返事は要注意です。
- 「今は忙しいのでまた連絡します」
- 「少し考えてからお返事します」
- 「今は検討中です」
これらは「契約の余地がある」と受け止められ、再びアプローチを受ける可能性が高まります。
明確に断るためのポイント
単刀直入に「入会しません」と伝える
- 主語と動詞をはっきりさせる。
「今後の連絡は不要」と明言する
- 電話・メールのやり取りを終わらせるための一言。
感情を抑え、淡々とした口調で伝える
- 感情的になると相手は説得の余地があると感じやすい。
- 事務的かつ冷静な態度が効果的。
- 「検討しましたが、入会はいたしません。今後のご連絡も不要です」
- 「婚活方法を変更しましたので、利用はしません。これ以上のお電話はお控えください」
【注意点】
- 「お金がない」「他で活動中」など条件付きの理由は避ける
→ 営業側が条件を解消する提案をしてくる恐れがあるため、かえって粘られます。 - 一度きっぱり断った上で、必要なら着信拒否やメールブロックを行うと安心です。
理由は短く簡潔に
しつこい勧誘を止める最短ルートは、長い説明ではなく「短く、結論を先に」伝えることです。
事情を詳しく語るほど、相手は説得材料を見つけて会話を延ばします。ここでは、短く簡潔に断るための考え方と、すぐ使える文例・想定問答をまとめます。
なぜ“短く簡潔”が効くのか
- 営業トークの余地を与えない(突っ込みどころを作らない)
- 事務的に処理しやすく、先方も引き際を判断しやすい
- 会話が長引かないため、心理的負担と時間コストを抑えられる
伝え方の基本設計(30秒で完了)
- 結論を先に:入会しない/検討を終了した
- 理由は一文:主観的で反論不能な内容に限定
- 連絡停止の明示:以後の電話・メールは不要
- 締めのひと言:簡単なお礼だけ(感情を乗せない)
避けるべき表現
- 条件付き理由:「お金が貯まったら」「今は忙しいので」
→ 条件を崩す提案(割引・分割・日時変更)に繋がる - 具体的事情の開示:「他社は○円」「親が反対で…」
→ 比較や説得の糸口になる - あいまい語:「一旦」「とりあえず」「前向きに検討」
→ 見込み客と判断され、再接触が続く
そのまま使える短文テンプレ
- 「入会はいたしません。」
- 「今回の件は見送ります。」
- 「本件の検討を終了しました。」
- 「他の方法で活動しますので不要です。」
- 「今後のご連絡は不要です。」
いずれも一文完結。必要なら最後に「ご案内ありがとうございました。」を添えるだけにする。
チャンネル別・簡潔フレーズ
■ 電話
- 「検討の結果、入会はいたしません。今後のご連絡も不要です。失礼します。」
(言い切ったら沈黙せず、そのまま通話を終える)
■ 対面
- 「今回は見送ります。これで失礼いたします。」
(席を立つ・名刺を返すなど終了の動作をセット)
■ メール/チャット
- 件名:入会見送りのご連絡
- 本文:
「検討の結果、入会はいたしません。以後のご連絡は不要にてお願いいたします。ご対応ありがとうございました。」
【よくある“食い下がり”への一言リプライ】
- 「理由を教えてください」
→ 「事情の開示は控えます。本件は終了です。」 - 「無料体験だけでも」
→ 「体験含めて不要です。」 - 「条件を調整します」
→ 「条件に関わらず利用いたしません。」 - 「時期を改めてご連絡を」
→ 「今後のご連絡は不要です。」
いずれも追加説明を足さず、同じ骨子で繰り返すのがポイントです。
【一度で終わらないときの最短フロー】
- 一文で結論+連絡停止(上記テンプレ)
- 以後は繰り返さず同文をコピペ返信
- 着信拒否・メールフィルタを設定
- なお継続する場合のみ、記録を残して相談窓口へ
- 日時・番号・担当名・内容をメモ
- 送受信メールは保管
連絡停止を明確に依頼する
結婚相談所からの勧誘は、一度断ったとしても連絡が続く場合があります。これは、相手が「時期を改めれば契約の可能性がある」と判断しているためです。
こうした再アプローチを防ぐには、「今後一切の連絡が不要である」ことを明確に伝えることが重要です。
なぜ明確な依頼が必要なのか
- 営業担当は、顧客リストを「連絡継続可」と「連絡不要」に分類して管理しています。
- あいまいな断り方だと「連絡継続可」に残されてしまい、再び勧誘されます。
- はっきりと「以後の電話・メールは不要」と伝えることで、営業リストから外されやすくなります。
効果的な伝え方のポイント
- 具体的な連絡手段を指定する
- 「電話・メールを含めて今後のご連絡は不要です」など、全ての手段を網羅する。
- 書面やメールで送ると、証拠が残るため効果が高い。
- 期限ではなく“永久的”な停止を求める
- 「しばらく不要」ではなく、「今後一切不要」と言い切る。
- 理由は添えても簡潔に
- 「入会の意思がないため」といった短い理由で十分。
「入会の意思はございませんので、今後のお電話やメールは一切不要です。」
■ メールで
件名:今後のご連絡について
本文:
「お世話になっております。先日のご案内については、入会の意思がございません。今後はお電話・メールを含め一切のご連絡をお控えいただきますようお願いいたします。」
■ 対面で
「今後はお電話・メールなどのご連絡は全て不要です。よろしくお願いします。」
【注意点】
- 証拠を残すために文章化
電話だけでは証拠が残らないため、必要ならメールや手紙でも通知する。 - 個人情報の削除依頼も有効
「お預けした個人情報も削除願います」と添えると、リストから外れる確率が上がる。 - 一度言ったら繰り返さない
同じ依頼を繰り返すと、相手が「説得の余地あり」と判断する場合がある。
最終手段として法的な対応を示す
何度断っても結婚相談所からの勧誘が止まらない場合、最後の手段として「法的根拠」を示して連絡を完全に断つ方法があります。
これは、感情的に怒るのではなく、冷静に法律や制度を持ち出して相手の行動を抑止するアプローチです。
使える法的根拠
- 特定商取引法
結婚相談所は「特定継続的役務提供」に該当します。契約後でも条件を満たせばクーリング・オフや中途解約が可能です。
また、電話や訪問による勧誘では、「契約しない意思を示した相手への再勧誘は禁止」という規定があります。 - 個人情報保護法
勧誘目的での個人情報利用を停止・削除するよう求めることができます。
実行手順
- 証拠を残す
- いつ、誰から、どんな方法で連絡があったかを記録する
- メールやメッセージは保存、通話は日時と内容をメモ
- 書面またはメールで「最終通告」
- 電話だけで済ませず、証拠が残る方法で送る
- できれば内容証明郵便や特定記録郵便を利用
- 再発時は相談機関へ
- 消費生活センターや消費者ホットライン(188)に連絡し、記録を提出する
貴社のご案内については、入会いたしません。今後の電話・メールなど一切のご連絡は不要です。
特定商取引法の「再勧誘禁止」に基づき、以後の連絡はお控えください。
必要に応じ、個人情報の利用停止および削除もお願いいたします。
これ以上連絡が続く場合は、関係機関へ相談いたします。
【注意点】
- 文面は簡潔かつ事務的に。感情的な言葉は避ける
- 「再勧誘禁止」「個人情報削除」など、法律上の用語を入れると抑止効果が高まる
- 一度通告したら繰り返さず、次はすぐ相談機関へエスカレーション
物理的な遮断も検討する
何度断っても電話やメールが止まらない場合、最後に頼れるのは「連絡そのものを物理的に遮断する」方法です。
感情的なやり取りや追加説明を避け、システム的に接触できない状態にすることで、ストレスを最小限に抑えられます。
物理的な遮断が有効な理由
- 相手に接触の余地を与えないため、説得や営業トークの入り込む隙がなくなる
- 言葉で断っても続く場合に、即効性のある対策となる
- 心理的負担や時間の浪費を大きく減らせる
主な方法とポイント
- 電話番号の着信拒否
- スマートフォンの機能で特定番号を拒否設定
- 非通知や別番号でかけてくる場合に備え、「非通知拒否設定」も併用
- 家族や同居人の電話番号も同じ設定にするのが安全
- メールアドレスのブロック・フィルタ設定
- 受信拒否リストに登録
- 「ドメイン単位」で拒否設定すると、新しいアドレスを使われても防ぎやすい
- 重要なメールと混ざらないよう、迷惑メールフォルダに自動振り分け設定
- SMS(ショートメッセージ)の受信拒否
- 通信会社の設定画面やカスタマーサポートでブロック依頼が可能
- SMS拒否+電話拒否を組み合わせるとより効果的
- 資料請求専用の連絡先を使う
- メールは専用アドレス(使い捨てアドレス)を利用
- 電話番号はIP電話や050番号など、後から変更しやすい番号を使う
- 郵送物の受取拒否
- 郵便局に「受取拒否」の旨を書いて返送
- 宅配便の場合は配達員に受け取りを拒否し、返送手続き
- 明確に「今後の連絡は不要」と伝える
- 同じ連絡が続く場合は、着信拒否・メールブロックなどを即設定
- 別の連絡先から再アプローチが来たら、同じ設定を追加
- 設定後も続く場合は、記録を残して公的機関へ相談
【注意点】
- 着信拒否やメールブロックは「証拠が残らない」ため、遮断前にやり取りの記録を確保しておく
- 遮断後に直接訪問されるケースもあるため、防犯意識を高めておく
- 別の番号やアドレスを頻繁に変えてくる業者は、早めに消費生活センターへ相談
|
結婚相談所は「向いている人」が大きく異なります。ここではタイプ別におすすめできる結婚相談所を5社厳選しました。 ※相談のみでもOK/入会を強制されることはありません。 ・IBJメンバーズ
|